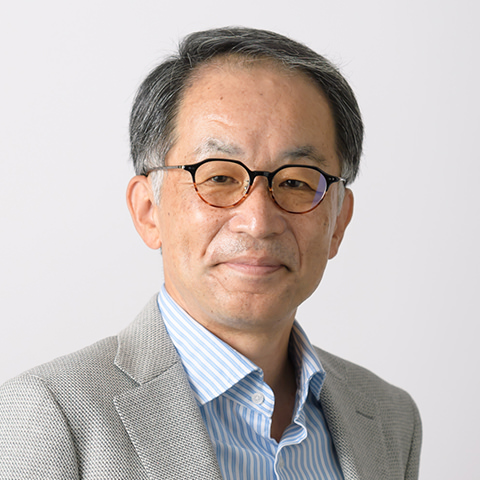パシフィックコンサルタンツグループでは、グループビジョン2030の達成に向け、2025年10月をスタートとする「中期経営計画2028 ~変革と成長、ともに未来の形を~」を策定しています。中期経営計画2028では、「持続可能な社会への貢献」「多様な人材の活躍」「グループ経営基盤の強化」を基本方針に掲げ、社会インフラサービスの先駆者として、未来を予測するだけではなく、構想力と実装力をもって「希望のある未来」を創造することを目指します。代表取締役社長執行役員の大本修が、中期経営計画2028に込めた想いをお話します。
INDEX
転機に立つ世界と日本
今、世界は大きな転換期にあります。各地で続く紛争や、気候変動に伴う自然災害の頻発化・激甚化は、社会に深刻な被害をもたらしています。国際社会は分断が進み、これまで築かれてきたさまざまな仕組みには、大きな軋みが生じています。日本においても、温暖化に起因する夏の異常高温やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れなどが増加し、農作物への被害も深刻化しています。地球温暖化が私たちの日々の暮らしに及ぼす影響の深刻さを、多くの人が肌で感じるようになりました。
さらに日本では総人口の減少や少子高齢化が予想を上回るスピードで進んでいます。2025年1月時点の日本人の人口は、前年からの1年で90万人あまり減少、これは和歌山県1県の全人口に匹敵する数字です。このまま推移すれば2050年代の早期に総人口が1億人を割り込み、2070年には約8,000万人にまで減少するとの推計もあります※。 1年毎の変化は大きくないかもしれませんが、このまま10年、20年が経過したらどうなるのか。私たちは戦後はじめて経験する時代の大きな分岐点に立たされていると言わざるを得ません。 これまでも私たちは「世界中の誰もが脅かされない、格差がない豊かなくらしを、実現すること」「すべての生命の源である美しい地球、その環境を守り、未来へ引継ぐこと」、この両立をステートメントとして掲げ、さまざまな社会課題の解決に取り組んできました。その歴史は1951年の米国法人パシフィックコンサルタンツの創立以来75年に及びます。その間、一貫して国土基盤の整備にかかわり、人々の豊かで安心な生活を実現するために、インフラエンジニアリングサービスを核としたさまざまな事業を推進してきました。しかし、今までの延長線上では、これから先の未来において、社会や環境の変化に十分対応し、更なる価値を提供することは、難しいと考えています。 インフラ整備は新たな段階を迎えています。世界に目を向けると、途上国では、発電所を設け、道路を通し、橋を架け、高速鉄道や地下鉄を建設するといったインフラの整備が一定程度実現しました。その一方で、激しい交通渋滞が発生し、社会経済活動を阻害しているため、車に依存せず、鉄道駅などを中心に都市機能を整備するTOD(Transit Oriented Development)と呼ばれる公共交通指向型の開発が、新たに求められています。国際協力により建設された鉄道や空港などの施設も、すでに20年、30年を経過したものが多くなりました。維持管理体制の構築、設備の更新や人材の育成のみならず、防災対策の強化や、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー・トランジションの推進なども求められています。 国内においてもインフラの老朽化が更に加速しています。高度経済成長期に一気に整備された道路や橋、上下水道などは、同時期に修繕・更新時期を迎えます。2030年には道路橋の54%、2040年には75%が建設後50年以上を経過したものとなりますが、埼玉県八潮市の下水道施設は、50年を待たず大規模な道路陥没事故の原因となりました。 その一方で、インフラの維持管理や更新は、人手や資金の不足から計画通り実施できていないケースが少なくなく、ある地域では、トリアージ(選別)により、橋梁撤去の可能性も検討されています。 今後さらに人手・資金不足が深刻化する中で、膨大なインフラをいかに運用し、維持管理、更新していくのか、都道府県や地方自治体単独では担えない場合に、官民連携を含めた広域的で包括的な取り組みをいかに成り立たせるのか、は喫緊の課題となっています。また、地球温暖化で頻発している局所的豪雨が引き起こす内水氾濫などの都市型水害にどう対応するか、そして、そもそも温室効果ガス削減への取り組みをどうやって加速させるのかも同様に重要な課題です。 また、まちづくりでは、車を中心とした開発から、人を中心としたものへの転換が、求められ、安心な市民生活に欠かせない防災、減災対策も、堤防や護岸の強化といったハード面だけでなく、土地利用そのものの再検討や適切な避難を実現するシステム整備など、ソフト面との複合化が求められています。 複雑化し、多様化する課題をいち早く見つけ、その解決を図るためには、インフラの整備に先頭で携わってきた私たち自身が変わらなければならないと考えています。私たちが、さまざまなパートナー企業と協力し、イノベーションを創出し、事業ポートフォリオの高度化を図ることで、グローバルな企業グループとして成長していくことが重要だと考えています。 私たちのステートメントと共通した未来を目指している企業は、インフラ整備に関連する業界以外にもたくさんあります。私たちは、もっと広く民間企業にアプローチし、抱える課題をより深く理解してソリューションを提供することで、「顧客起点の課題解決」に力をいれていきます。同じ志を持つ顧客や事業パートナーと協働し、新たなソリューションを共に創造しながら、目指す未来の実現をリードしていきます。 そのため、2025年10月にスタートした中期経営計画2028において、パシフィックコンサルタンツグループをホールディングス化し、新たに国際事業会社を設立するなど、グループ企業構造の大胆な改革を進めることにしました。ホールディングス化は、建設コンサルタントという枠にとらわれることなく、事業ポートフォリオの高度化をはかり、社会により高い価値を提供する企業グループとなるという意思表示です。国際事業会社を、二番目の柱として成長させながら、その次の柱となる従来のコンサルティング事業とは異なる新たなビジネスを模索し、次の事業会社の設立を目指します。グループとしての経営戦略を明確にし、国内外の多様な課題の解決に取り組んでいきます。 グループ企業構造の変革と並行して、人材への積極的な投資を進めています。多様な人材がそれぞれの力を発揮し、成長できる基盤を整えることで、グループ全体の総合力を最大化することを目指しています。その一環として、中期経営計画2028では、非財務目標(KPI)として女性管理職比率15%、外国籍社員数110人、所定外労働時間20%削減など具体的な目標を設定しました。また、キャリアパスのあり方も見直しを進め、従来の「一本の上り棒」のような一方向型から、上下左右・斜めにも進める「ジャングルジム型」へと変換します。マネジメントへの昇進だけでなく、技術を極めたい従業員には、スペシャリストとして成長できる選択肢を用意するなど、より柔軟で一人ひとりの想いに応えられるものに変えます。従業員が、その時々の状況や希望に沿ったかたちで長く働き続け、成長できる仕組みを整えることで、多様な人材の力を結集し、新たな企業成長を実現していきます。 中期経営計画2028に基づく具体的アクションのひとつとして、2025年9月1日より共創パートナーとの新サービス、新市場の創造に向けてイノベーションを起こすオープンイノベーションプログラム「パシフィックコンサルタンツ共創プログラム2025」をスタートしました。 このプログラムは、持続可能な社会の実現に向けて、当社が長年にわたり培ってきた技術や知見と、スタートアップ企業が持つ革新的なアイデアやスピードを掛け合わせて、新たな価値の創出を目指すもので、災害レジリエンスの強化、GX(グリーントランスフォーメーション)の実装など、具体的な4つのテーマの下に共創パートナーを広く募るものです。このプログラムの活用以外にも、新たな技術やサービス開発に取り組むベンチャー企業と連携しながら、従来の私たちにはなかった技術やサービスを共に創出できる体制を整え、新たなビジネスの創出・成長を目指していきます。 次の時代のインフラをどう構築するのか新たに問われるなか、私たちは従来の枠や発想にとどまることなく、インフラエンジニアリングを核とした先進的なサービスを提供し、新たなパートナーとともに、新規事業に積極的に挑戦します。 パシフィックコンサルタンツグループは、新たなソリューションを創造しながら、2050年、そしてその先の未来において、目指す社会の実現をリードします。
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」出生低位推計
これまでと同様の対策では豊かな未来は築けない
新たなグループ経営体制に移行

多様な人材の活躍で複雑化する社会課題に応えていく
オープンイノベーションを積極的に展開